6月終盤、本来ならば梅雨の真っ只中で山行には向かない季節ですが、今年は例年よりも降雨量が非常に少なく、この時期でも夏本番のような晴天と猛暑が続いていました。
それにも関わらず、山行を計画していたここ2日間だけは天気が悪く、本来ならば他の山でのテント泊を計画していたのですが、急遽計画を変更。
比較的天候がマシな毛無山への登山にシフトしました。
今回は、先日大菩薩嶺に一緒に行ってくれたリフティング技術が抜群の後輩と、払暁の時間から登り始めて、午前中のうちに下山する行程で毛無山に挑みます。
登山データ
| 活動時期 | 時間 | 歩行距離 | 累積標高 | コース定数 |
| 2025年6月26日(1Day) | 6時間22分 | 5.6km | 1,095m | 24 |
夜の山道

6月26日の午前3時半、真っ暗な駐車場からスタートです。
そこにあるBOXに封筒が入っているので、駐車料金500円を封入して投函します。

毛無山の登山口はこちらです。
車が進入しないように鎖が張られています。
久々に夜の山道を歩けると思うと、この静寂に包まれた雰囲気と相まってゾクゾクしてきました。

スタートして10分ほどで、毛無山登山道と、地蔵峠方面への分岐があります。
ここから看板通り東へ進めば、およそ2時間ほどで地蔵峠に辿り着きます。
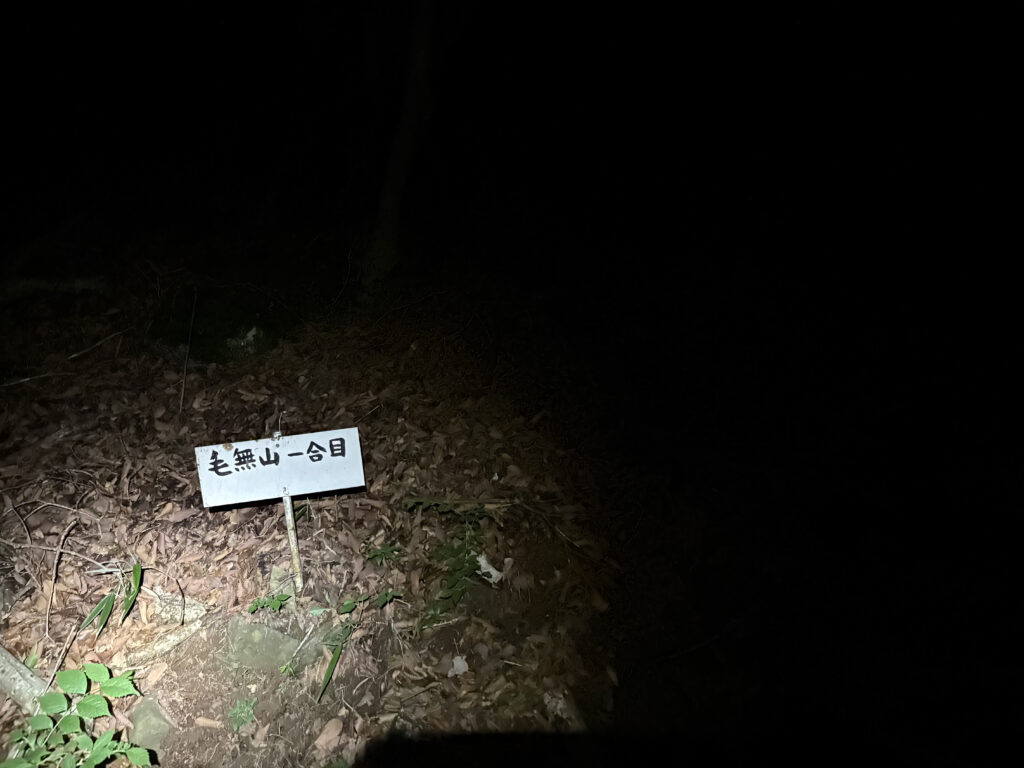
暗闇を進み続けると、毛無山一合目の看板が現れました。
毛無山は、一合目から九合目まで丁寧に看板が設置されており、今どれくらい登ったのかが非常に分かり易いです。

3時58分、明け遣らぬ空に日本一の山が覗いています。
こんな光景を見てしまうと、もっと上からの景色を早く見たくて、気持ちまで逸ります。

東の空は明るくなりつつありますが、足元はまだ薄暗いままです。
登山道には、道迷いを防ぐためのロープや看板が多く設置されているため、こんな時間から出発するような変態登山者には本当に有難いです。
顕現する険しい道筋

ヘッドライトの光が、目の前のロープを照らしています。
毛無山の道のりは、このようなロープを活用した急登がひっきりなしに現れるので、飽きが来ません。

午前4時を回ると、いよいよ富士山が鮮明に見えるようになってきました。
靉靆たる雲が頂を覆っており、まだその姿を完全に拝むことはできません。

4時11分、毛無山二合目です。
徐々に空が明るくなると共に、地面や周りの様子が色づいてきます。
真っ暗闇の登山道は、自分の足元と黒い樹木の影しか見えていなかったため、どんな道を歩いてきたのかは、下山時のお楽しみです。

道中は、相変わらず急登が続きます。
登山道は、木の根や大き目の岩が行く手を阻む場面が多く、そういった場所はロープが用意されています。
ロープを確実に掴むためのグローブが非常に役立ちます。

ロープの場所を越えると、またロープが現れます。
中には異常に汚いロープがあるので、掴んだ後のグローブが黒茶色に変色してました。

立て続けにロープの場所を乗り越え、一息ついたところで倒木があります。
手応えのある道に集中していたので、いつの間にか周りが明るくなったことに気付きませんでした。
これにてヘッドライトはお役御免です。

再三ロープの場所が現れました。
短時間にこれだけロープ箇所を越えてきたので、流石に慣れてきました。
岩に靴の前足部を押し付け、爪先に全ての体重をかけて踏ん張りながら登っていきます。
今回スカルパのゾディアックテックを履いていますが、こういう場面でソールの硬い靴が真価を発揮します。

4時42分、毛無山の四合目です。
3合目からここまでの区間、急登際立つ難路でした。

4時47分、標高1,350m程の場所にレスキューポイントと呼ばれる開けたスポットがあります。
休憩にピッタリの場所なので、急登で消耗したエネルギーを補給して先に進みます。
五感で楽しむ森林浴

5時ちょうど、東の山肌から太陽が昇ってきました。
まだ暑くない時間帯、陽が出てからの数分間が非常に心地よく、少し足を止めて太陽と森林のパワーを全身で感じます。
一気に明るくなった周りの風景を楽しみながら、正面に目を向けて歩を進めます。

5時6分、毛無山の五合目です。
昭和の雰囲気漂う看板も粗雑に置かれており、ここだけ時代が止まったような感覚です。

完全に明るくなって周りを見渡します。
目で楽しむ鮮やかな緑、鼻で楽しむ土と樹の香り、耳で楽しむ鳥や蛙の鳴き声・・・
最も穏やかな時間が流れ、自然の醍醐味が濃縮された最高のひと時です。

五感をフル活用しながら森林浴を楽しんでいるところですが、登山道に集中しないといけません。
道幅が広がり、登山道に見えるような誤った道に進んでしまう危険があります。
この日の午前中は視界が良かったので問題ありませんでしたが、霧などで視界が制限された状態だと、普通に道迷いが起きてしまいそうな地形となっています。

富士山の方を振り返ると、見えそうなのに、その姿を完全に捉えることは未だできません。
どうやらこの瞬間は雲がなく山頂まで明瞭に見えそうなので、早くその雄姿を見たいという思いが勝手にペースを早めてしまいます。

5時46分、毛無山7合目です。
徐々に気温が上がってきて、一緒に来てくれた後輩の飲み水が少なくなってきました。
夏場の午前中から登るのであれば、2リットルくらい水は欲しいところです。
鹿屋体育大学の山本教授の本にて、
“登山中に必要な水分量=自重(体重+ザック)×5×行動時間 “
という計算式を見ました。
なお、一度にがぶ飲みすると消化器官で吸収するうえで効率が悪いので、30分を目安にちょっとずつ補給することを意識していきたいですね。

7合目を過ぎても、開放的な景色はまだ先です。
それでも、このような大き目の岩を登る場所やロープ、土の穏やかな傾斜の道が代わるがわる出てくるので、変化に富んだ道を楽しむことができます。

6時5分、毛無山八合目です。
登山中は気にしていなかったのですが、この看板の文字が手書きですね。
観光名所として有名になった山やとかメジャーな山だと、こういう案内表示は凝ったデザインのものが多いです。
そんな中、白無地に必要最低限の情報だけ書いてある毛無山の看板は、独特の風情を感じますね。

毛無山の登りで、一番時間をかけたのはここです。
やや長めの直登をロープを手繰りながら登っていくのですが、土の斜面は滑りやすく、加えて掴んだロープ自体も滑ります。
登り切った後のグローブが信じられないほど汚れていました。

またロープが出てきました。
すでに登山口から10か所以上ロープを見てきた気がするので、流石に閉口するしかありません。
森林浴は十分楽しんだので、そろそろ開放的な景色が見たいな・・・
と思っていた矢先、ずっと見たかった景色が漸く見えてきました。
富士を望む展望台

6時15分、「富士山展望台」なる場所に来ました。
ここまで富士山はチラチラ見えていたものの、その全容は全然見えていませんでした。
そんな中こんな看板がいきなり現れたら、期待せざるを得ません。
さあ、富士山を見るぞ!

目の前に現れたのは、期待以上に綺麗なパノラマでした。
やはり富士山は一際異彩を放つ、日本一の山だと改めて思います。
眼下に広がる長閑な朝霧高原の風景と、その背後に聳え立つ美しい円錐形の富士山、そして雲容烟態の眺めが調和して、自然と笑いが込み上げてきました。

南側に目をやると、富士宮市の街並み、そして奥に駿河湾が見えます。
山から見える海は私の大好物です。

富士山の頂上がはっきり見えたのは、ほんの数分だけでした。
日本一の山を取り巻くかの如く次々と雲が湧いてきて、山頂を覆い隠します。
それはそれで、日本一の山が持つ格というか、高貴なイメージに合っている気がします。
これが見られただけでも大満足ですが、今回の目的は毛無山です。
頂上まではもうひと踏ん張り。高揚した気分のまま、一気に山頂まで登っていきます。
天子山地の稜線

富士山展望台を発ち、6時30分、毛無山九合目です。
もうここまで来れば急登は無くなります。

6時31分、地蔵峠分岐点に到着しました。
毛無山を最高点とする天子山地の稜線上です。
稜線といっても、北アルプスのような開放的な稜線ではなく、背の高い木々に囲まれた道が連なっています。

南アルプス方面は縹渺とした雲が広がっていて、その姿をはっきり見ることはできません。
最近南アルプスには全然行っていないので、久々に行きたいです。
こうして見えない景色の先にある南アルプスに思いを馳せます。

稜線上はほとんど傾斜がなく、10分程で毛無山に到着するので難しくありません。
地面はちょっとぬかるんでいるものの、全体的にとても歩きやすいです。
この道を真っすぐ往くと、雨ヶ岳や竜ヶ岳まで繋がっています。

あそこに見えるのが毛無山の山頂です。
美しい緑に囲まれた場所で、「毛無」の由来と言われている、山頂に樹木が少ない様子とは異なった景観となっています。
(毛無山の名前の由来は諸説あります)
毛無山の山頂

6時42分、日本二百名山に数えられる、毛無山(1,946m)の頂上に着きました。
ここは山梨県身延町と、静岡県富士宮市の境目となっています。

この看板の向こう側には、本来は富士山が見えるのですが、今は雲がかかっていて何も見えません。
ただ、上空は風が強く雲が早いスピードで流れていくので、タイミングによっては富士山が姿を現します。

また、この場所は一等三角点があります。
ちなみに、毛無山は “一等三角点百名山” の一座として名を連ねています。
毛無山の最高点はこの場所ではなく、もうちょっと北東に進んだ場所にありますが、今回我々はここまでの計画となっているため、この先には進みませんでした。

富士山はしばらく雲の中に隠れており、天気も下り坂になっていくため、流石にもう見られないか・・・
と思っていた時、雲が払われ紺碧の空が!
そして、最後に富士山の頂の部分だけが顔を覗かせました。
雲に浮かぶ富士山の山頂、幻想的な光景です。
この後すぐに濃い雲が視界を覆ってきて、この後は下山するまで青空を見ることはありませんでした。
今思えば、この晴れ間はとても貴重なタイミングでしたね。
少しだけでも、富士山をこの山頂から見たいという願いが叶って良かったと思いました。
雲に包まれた下山路

7時半に毛無山を後にし、下山します。
下山間際に見られたひとときの晴れ間を最後に、すっかり霧に包まれました。

地蔵峠分岐点まで戻ってきました。
今回はいつも使っているミラーレス一眼を、本来テント泊で使う予定だったデカいザックに置いてきてしまったので、全部iPhoneで撮影しています。
なお、ずっと使っていたiPhoneXRは前回の那須岳登山直後に壊れたため、新たに手に入れたiPhone16で写真を撮っております。

さっき凄い絶景を見せてくれた富士山展望台まで戻ってきました。
同じ場所に戻ってきたとは思えないような景色となっていますね。
待っていても天候回復が見込めないので、安全に下山することに集中します。

こういう天気になると、先ほど懸念していた道迷いが起こりがちです。
勢いのままどんどん下山してしまうと、いつの間にか道を外れちゃうことが過去に何度もありました。
時間的余裕はかなりあるので、立ち止まってでも自分の現在地を見失わないように、マメに確認しながら下ります。

後輩は丁寧な足運びで、頑張って下っています。
彼は今回の為に60リットルのザックを購入したのですが、大型ザックのデビュー戦はテント泊ではなく日帰りの毛無山での使用となりました。
こんな風に登山が好きになってくれて、本当に嬉しい限りです。

登りの時点である程度警戒していましたが、急すぎて足元が見づらい場面が多く、下山では苦労します。
静岡県の山のグレーディングでは、毛無山のグレードは五段階のうち「B」となっています。

8時56分、レスキューポイントまで下ってきました。
ここはヘリコプターの救出が可能な場所で、もし病気や怪我などで下山困難になった場合は、119番するように!
という内容が看板に書いてあります。

四合目と三合目の間が、一番ロープが多いです。
上から見ると、ちょっと高度感があって身構えてしまいます。
先日ボルダリングをしてきたことを思い出し、なるべくロープを使わずに下ってきましたが、ここだけはロープを大いに頼らせていただきました。

9時26分、不動の滝見晴台に来ました。
登りの時も通ったのですが、真っ暗な中滝の流れる音しかしなかったので、下山にてやっとお目にかかれました。
迫力満点の勇ましい滝も良いですが、こういう気品を感じる落ち着いた流れの滝も好きです。
時間を忘れてずっと見ていたくなります。

だいぶ高度を下げてきました。
あそこに、ふもとっぱらのキャンプ場が見えます。
平日なので、張ってあるテントは指で数えられる程度しかありません。

山行の終わりが近づいてきました。
登りでは暗くてどうなっているか分からなかったので、最終盤で全容が分かって非常に面白いです。
明るくなるまで普通の岩場だと思っていましたが、枯れきった沢でした。

9時58分、毛無山の登山口まで戻ってきました。
今回のハイライトは、何といっても富士山展望台から見えた壮大なパノラマです。
寸刻の間しか見られませんでしたが、振り返ってみると、それがむしろ特別な時間だったと思います。
最近の山登りは既に行ったことのある山に再挑戦することが多いですが、今回の毛無山は初めて訪れた山地です。
初めて足を踏み入れる場所は、どんな山でも未だ見ぬ景色や雰囲気に気持ちが高揚します。
毛無山登山を通じて、登山始めたての頃に感じた登山の醍醐味を改めて実感することができました。
今回来てくれた後輩にも感謝です。山登りにどんどん挑戦していく様子を見ていると、本当に嬉しくなります。
突然計画を変更して赴いた毛無山でしたが、初心の頃の気分が蘇る、本当に素晴らしい山行となりました。
6月26日
3:30 毛無山駐車場発
3:56 毛無山一合目
4:11 毛無山二合目
4:22 毛無山三合目
4:42 毛無山四合目
4:47 レスキューポイント
5:06 毛無山五合目
5:27 毛無山六合目
5:46 毛無山七合目
6:05 毛無山八合目
6:15 富士山展望台
6:30 毛無山九合目
6:31 地蔵峠分岐点
6:42 毛無山(三角点)着
7:30 毛無山(三角点)発
7:40 地蔵峠分岐点(下り)
7:47 富士山展望台(下り)
8:56 レスキューポイント(下り)
9:26 不動の滝
9:58 毛無山駐車場着








